「姉小路氏城館跡と飛騨の中世」展と古川考古学散歩
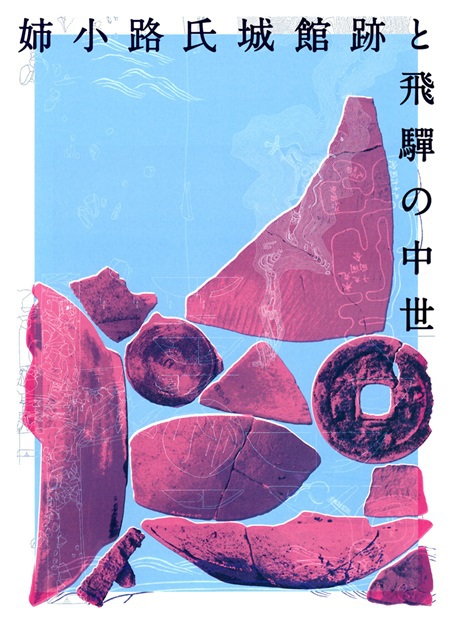
(飛騨市美術館企画展カタログから)
学習会のお知らせ
会員以外の方も参加できます。事前申し込み不要。
12月3日(日) 9時40分頃 飛騨市美術館前集合
「姉小路氏城館跡と飛騨の中世」展見学(学芸員ギャラリートークに参加)
その後、古川考古学散歩(増島城跡、塔の腰廃寺塔心礎 等)
参加費 会員以外の方は、入館料200円お願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★本会に質問や感想、情報提供などがある方は
下記メールよりお気軽にご連絡ください。
(*を@に変えて送信してください)
jo-lucky*hi3.enjoy.ne.jp
★本会の成り立ち、過去の活動、
刊行物等はこちらをご覧ください。
飛騨考古学会PDF





